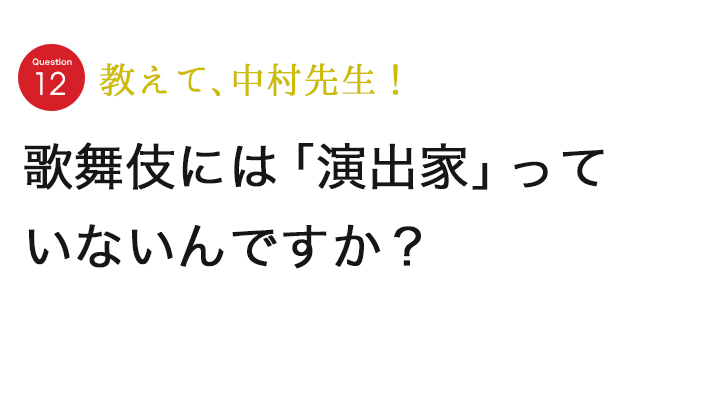おや、なかなか鋭いところに目をつけましたね。確かに、歌舞伎の場合、明治以降に創られた「新歌舞伎」と呼ばれる作品郡や、最近、ジャンルの違う宮藤官九郎や野田秀樹などの作家が作品を提供するケース以外には、あまり「演出:○○」とはチラシに書いてありませんね。
これは基本的な原則、と考えていただければ良いと思うのですが、一本の芝居の中で、主役を演じる役者が「演出」を兼ねている、と思っていただいて良いでしょう。
江戸時代には、「演出」という言葉はありませんでした。これは、明治維新以降、西欧の思想が流入する中で、「作品の意図を汲み取り、解釈のもとに舞台をまとめ、統一を図る」という意味合いでできたものです。
歌舞伎の場合は、主役を演じる俳優が、自分で工夫した演技や型などを、共演の俳優と相談しながらまとめていく役割を担っているケースが多く見られます。それが、今で言う「演出」という言葉に相当するのではないでしょうか。
場合によっては、遥か昔に亡くなった方の名前が「演出」として掲載されていることもありますが、これは、その作品の初演の形を創り上げた先輩に対する敬意の現われ、と考えていただいてよいでしょう。
ただ、これからは、現代の観客の生理やテンポに合わせて、今までの古典作品の味わいを損なわないように、作品のカットや科白の言い換えなどに心を砕くことも歌舞伎の課題の一つです。
こうした、「テキストレジー」に当たる作業を、演劇の世界では「補綴」(ほてつ)と呼び、これは歌舞伎に限ったことではありません。こうしたことからも、「演劇は時代と共に生きている」ということが証明されるんですよ。